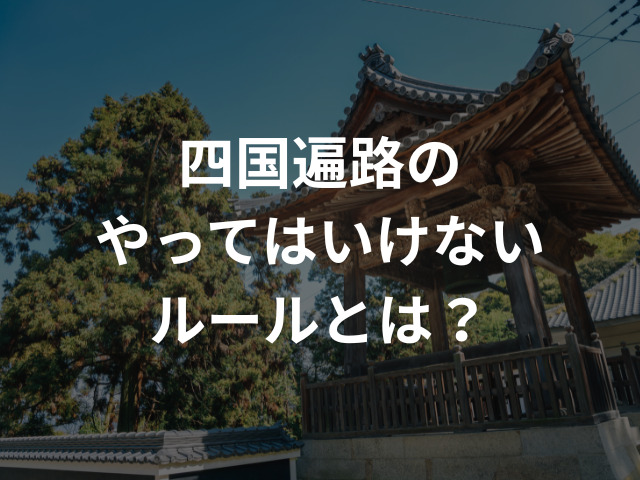今回は「四国遍路のやってはいけないルールとは?八十八ケ所巡礼の基本と逆打ちの極意を徹底解説!」と題しましてお送りしていこうと思います!
四国遍路は、弘法大師・空海の足跡をたどる全長1,200 kmの巡礼旅です。
四国遍路に挑むなら、まず「知らずに破ればご利益を逃すやってはいけないルール」を理解することが欠かせません。
全八十八霊場をめぐる88ヶ所巡礼の長丁場では、マナーを守るかどうかが旅の質を大きく左右します。
また、近年ブームの逆打ち(88番札所から1番札所へ逆回り)に臨む人も増えていますが、逆打ちには道標の少なさや時短メリットなど独特のリスクと魅力があります。
そこで本記事では、やってはいけないルールを10項目に整理し、成功率を高める88ヶ所巡礼の下準備と作法を徹底ガイドとして紹介していきたいと思います。
読み終えるころには、初心者でも安心して“功徳を最大化”できる旅支度が整うと思います!
※下記に動画で解説しているものもあるので、そちらも参考に!
Contents [hide]
四国遍路&逆打ちとは?
【松山ケンイチさんの四国遍路】
俳優の松山ケンイチさんが車で四国八十八ヶ所を巡拝。初日の動画がYouTubeにアップされています。
一番札所霊山寺からの順打ちで安楽寺の駐車場でランチタイムとなっていました。#四国八十八ヶ所 #四国遍路#松山ケンイチ #御朱印 #御朱印巡り #仏像 pic.twitter.com/7iS5xuk5nb
— 温泉山 安楽寺ガチャガチャ企画部 (四国八十八ヶ所 第六番札所) (@onsenza_anraku) June 24, 2025
四国遍路は、弘法大師・空海ゆかりの88ヶ所霊場をめぐる1,200 kmの巡礼になります。
順打ち(時計回り):1番霊山寺→88番大窪寺にまわるいわば王道のまわり方になります。
この順打ちで初心者でも道標が多く安心して巡礼することができます。
逆打ち(反時計回り):88番→1番へ逆走するまわり方になります。
昔から「三度で順打ち一度分の功徳」とされ、ご利益アップを期待して挑戦する人が増加中。
いわば逆打ちを完走した方は順打ちの3倍のご利益があるとされています。
しかし逆打ちは道標が少なく難易度アップ、だからこそ「修行」としての価値が高い。
特に軽い気持ちで逆打ちに臨むと逆に不幸なことが起こってしまうという話もあります。
とにかく逆打ちであっても基本の参拝マナーは同じです!
より一層強い気持ちでないと、逆打ちは危険な巡礼になりかねません。
「やってはいけないルール」を守ることが、88ヶ所すべてのご利益を正しく受け取る第一歩でしょう。
次の章では、ご利益を正しく受け取るためのやってはいけないマナーを10個紹介していきたいと思います。
やってはいけないルール10選を紹介!
たかおかななは、旅に出ます。
88ヶ所のお寺を巡る、四国遍路
1400kmの旅路を徒歩で回ってきます。地域創生のために自分が
発信者として、
起業家としてできることそれは圧倒的原体験をもとにした
現場の声を届け、聞き、形にすることきっと涙ぐむほど素敵な景色もあれば… pic.twitter.com/GJWrJDMlS8
— 高岡奈々葉@ カルチャークリエイター
(@nanaha_mrt) June 7, 2025
それでは、正しく巡礼するためのやってはいけないルールについて紹介していきます。
10個ありますので、ぜひ参考にしていただければと思います!
①山門をくぐる前に合掌しない
山門は俗世と聖域を分ける“結界”になります。
ここで合掌し一礼することで「今から修行に入ります」という宣言になり、雑念を外に置いて心を清める効果があります。
合掌を省くと参拝前の“無礼な飛び込み”と見なされ、霊場の雰囲気を乱すだけでなく、自分自身も巡礼モードに切り替わりません。
撮影や地図確認で山門前を素通りしがちですが、いったん立ち止まり、深呼吸して合掌してから一歩を進めましょう。
②金剛杖を本堂・大師堂へ持ち込む
金剛杖は「同行二人(どうぎょうににん)」—弘法大師と常に二人連れで歩むことを示す大切な法具です。
堂内へ同伴させるのは“大師を背負って参拝させる”形になり失敬です。
正式には入り口脇の杖立てに立てるか、堂前の壁に立て掛け、先端が傷まぬようキャップで保護します。
杖先に付いた土砂を払い、「大師さま、しばしお休みください」と心のなかで唱えると丁寧なマナーとなりますのでぜひやってみましょう。
③境内で飲食・喫煙
札所は寺院であると同時に修行の場です。
食事の匂いやタバコの煙は修行僧や参拝者の読経を妨げ、浄域を俗化させてしまいます。
どうしても補給が必要な場合は境内を出てから、あるいは休憩所・指定ベンチなどで最小限に行い、ゴミは必ず持ち帰るのが基本。
特に逆打ちの山寺では火気厳禁区域も多く、林野火災の危険もあるため注意が必要です。
④納経所でスマホ通話や大声
納経所は御朱印を通して功徳を授かる“儀式空間”。
応対する寺務員や僧侶も仏に仕える立場であり、声高に話すのは礼を失する行為です。
電話が鳴りそうなときはマナーモードにし、列に並ぶ間も静粛を保ちましょう。
代金を渡す際は両手で差し出し、「お願いします」「ありがとうございます」の一言を添えると好印象です。
⑤朱印だけもらい読経を省略
読経は“諸仏への請願”であり、朱印は“修行を証明する印”です。
読経なしで朱印だけ求めるのは、卒業式に出席せず卒業証書だけ受け取るようなものです。
時間がない場合でも、本堂と大師堂で般若心経と真言を最低一巻ずつ唱えるのが望ましいです。
なので、経本を忘れた場合は堂内の掛軸やスマホ経本をそっと参照し、心を込めて唱和しましょう。
⑥写真撮影禁止エリアでシャッター
ご本尊や秘仏は“信仰の核心”であり、カメラに収める行為は霊力を薄めると昔から忌避されてきました。
撮影OK箇所でもフラッシュやシャッター音が修行の妨げになるため要注意です。
札所によっては「堂内撮影禁止」や「御影堂は撮影可」などルールがまちまちなので、事前に掲示を確認しましょう。
疑わしい場合は撮らないのが無難です。
7. 札所の敷居を踏む
敷居は「結界」を象徴し、外界の穢れを内へ持ち込まないための境目です。
踏むと結界を汚し神仏を冒涜することになり、古来より大きなタブーです。
段差が低く見落としがちですが、必ず軽く跨いで入堂し、退堂時も同様に跨ぐこと。
雨天で滑りやすい場合は足元をしっかり確認し、杖を突かずに静かにまたぐと美しい所作になります。
⑧白衣を夜着代わりにする
白衣(びゃくえ)は“死装束”を意味し、「たとえ道中で倒れてもそのまま荼毘に付される」という決意の表れ。
寝巻きや室内着として使うのは、儀礼服をパジャマにするのと同じく不敬です。
宿坊や旅館では白衣を脱いで丁寧に畳み、ハンガーに掛けるか清潔な袋に保管し、翌朝また身を清めて着用しましょう。
⑨お接待を断固辞退or無言受け取り
四国独特の“お接待文化”は、施す側が徳を積む仏縁行為です。
頑なに拒むと相手の功徳を阻害することになります。
受け取る際は笑顔で合掌し、「おかげさまで歩けます」「ありがとうございます」と感謝を述べるのが礼儀。
もし飲食物を頂く場合は、健康上の理由で食べられない旨を丁寧に伝え、代わりに納札を渡すなどして気持ちを返しましょう。
⑩ゴミの放置
遍路道は弘法大師を慕う先人たちが守り継いだ“歩く文化遺産”です。
ペットボトルひとつでも景観を損ね、後の巡礼者の信仰心を削ぐ原因になります。
ゴミ袋は必携とし、山間部や無人札所では持ち帰るのが大原則。
キャンプを伴う逆打ちの際も焚き火跡や灰を残さず「来た時よりも美しく」を徹底してください。
このように10個紹介してきましたが、これから巡礼される方はぜひ参考にしてみてくださいね!
次の章では、正しいお参りの手順を紹介していきたいと思います。
八十八ケ所巡礼の基本!正しいお参りの仕方を紹介!
今年から四国八十八ヶ所、車遍路してて
愛媛制覇してきたpic.twitter.com/NwoI1JeHUF
— らび
(@Labi3310) June 23, 2025
それでは正しいお参りの仕方について紹介していきたいと思います。
①山門で一礼
山門は「俗世(現実世界)」と「聖域(霊場)」の境界線。
ここで一礼するのは、心身を整え「これより仏さまの世界に入らせていただきます」という敬意と覚悟の表れです。
帽子を取り、荷物を整え、静かに一礼してから境内へ入りましょう。
一礼せずにそのまま通過するのは、神社で鳥居をくぐるときに無言でダッシュするようなものです。
まずはここで心を“巡礼者モード”に切り替えることが大切です。
②手水舎で清める
境内に入ってすぐに見えるのが手水舎(ちょうずや)。
ここで手と口を清めることで、身体だけでなく心の穢れも払うという意味があります。
正しい作法は:
- 柄杓で右手 → 左手を清める
- 左手に水を受けて口をすすぐ(柄杓に直接口をつけない)
- 左手を再び清める
- 最後に柄杓を立てて柄を洗う
“手水”を省略すると「汚れたまま仏前に立つ」ことになり、礼を失する行為とされます。
③鐘楼で静かに鐘を一突き
鐘楼(しょうろう)にある鐘は、仏さまへの参拝を知らせ、邪気を払い、自身の煩悩を清める意味があります。
鐘をつく際は、必ず「一突きのみ」が基本。
何度も鳴らすのは“我欲が強い”と見なされ、周囲の巡礼者にも迷惑になります。
また、深夜や早朝など時間帯によっては鐘撞きが禁止されている札所もあるため、周囲の案内板に従いましょう。
※鐘を撞かずに通過することはマナー違反ではありません。混雑時は遠慮するのも配慮の一環です。
④本堂で線香・ロウソクを供える
本堂は、その札所のご本尊(主尊)が祀られている最も神聖な場所。
まずロウソクを灯し、次に線香を立てます。
それぞれの意味は:
-
ロウソク=光明を灯す(仏の智慧)
-
線香=香煙で穢れを祓い、心を整える
火を扱う際は他人のロウソクや線香に火を移す「もらい火」は控え、自分で点火しましょう。
また、線香は1本だけでOKですので大量に立てて煙を出すのは仏前を曇らせ、迷惑になることは避けましょう。
5. 般若心経・御本尊真言を唱える
参拝の核心は“読経”。般若心経を一巻、続けてその札所のご本尊に対応する真言(短い祈りの言葉)を唱えます。
声は大きくなくてOK。
心を込め、意味を意識しながら唱えることが大切です。
スマホの経本アプリを利用しても問題ありませんが、なるべく紙の経本を使うと集中しやすく、姿勢も整います。
※読経の順序例:
-
開経偈
-
般若心経
-
御本尊真言
-
回向文
暗記できていなくても、気後れせず自分のペースで読経すればOKです。
⑥納札を箱へ納める
読経後は、名前・住所・願意などを記した「納札(おさめふだ)」を専用の箱に納めます
これは「この場に自分の願いと心を捧げます」という“記名の証し”。
納札には白・赤・金などの色がありますが、巡礼の回数によって使い分けます:
-
白札:1〜4回目
-
緑・赤札:5〜24回目
-
銀札:25〜49回目
-
金札:50回以上
無理に色を気にする必要はなく、白札だけでも十分ですが、手書きで心を込めることが大事です。
⑦大師堂で同じ手順を繰り返す
本堂の次は弘法大師を祀る「大師堂」へ。
ここでもロウソク・線香を供え、般若心経と弘法大師真言「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」を唱えます。
大師堂は“同行二人”の象徴でもあり、「常に共に歩いてくださる弘法大師に感謝を伝える」場所。特に逆打ちの場合、道中の無事を祈る意味合いが強くなります。
※順番としては「本堂→大師堂」の順が基本。逆にすると作法が乱れるとされます。
⑧納経所で御朱印を受ける(1ヶ所300円程度)
最後に納経所で御朱印(納経印)をいただきます。
これは「きちんと読経と参拝を終えました」という証明であり、後々の大切な記録となります。
渡し方や言葉づかいも礼儀正しく:
-
納経帳を両手で差し出す
-
「お願いします」→「ありがとうございます」
また、御朱印は“スタンプラリー”ではありません。読経もせずに集めるのは修行を省いた結果として意味が薄れます。
※納経料は現金で用意し、お釣りが出ないようにしておくとスマートです。
次の章では逆打ちに行かれる際の成功のコツや注意点について見ていきましょう。
逆打ち成功のコツと注意点を解説!
四国遍路は、88のお寺があるから、人々が回り始めたのではなくて。訪ねるべき山野があるから、人々が回り始め、寺社仏閣ができた。
私がお寺をあまりアップしないのは、訪ねるべき山野が原点だし、山紫水明のほうが、理解されやすいと思うから。
ここ、元禄時代の地図にも、記録あったわ。 pic.twitter.com/tKOpYSvBRk
— 山登りするハリネズミ (@minohitotu) June 28, 2025
ここでは逆打ちのコツや注意点について書いていきたいと思います。
- 時期選び:夏は熱中症、冬は降雪エリアあり。おすすめは春・秋。
- 移動手段:公共交通は逆方向ダイヤが少ない。レンタカー+徒歩区間を混在させると効率UP。
- 札所番号の逆順メモ必携:公式ガイドブックは順打ち基準。逆番号インデックスを作成。
- 時間配分:1日平均15〜20 km歩行+3〜4札所で計画。
- 宿泊:宿坊や民宿は前日までに逆順で予約。
逆打ちでは人流が少なく静寂を味わえる一方、迷いやすいです。
オフライン地図アプリにGPXデータを入れておくと安心なので、事前に準備しておきましょう。
快適に歩くための持ち物&服装チェックリストを紹介!
愛媛県を遍路中
60番札所・横峰寺さんは、四国一の霊峰石鎚山(1982m)の北側中腹750mの所に。88ヶ寺で3番目に高くても暑
16時になると毎日爽やかな風。両手を広げて山道を歩くと気持ちいいー
先々週、大雨で石鎚山登拝途中で引き返したので晴天の石鎚山が嬉しい上の売店のところ天、美味
pic.twitter.com/2QpU93YI88
— 家田荘子 (@shokoieda) June 5, 2025
最後に持ち物や服装についてみていきたいと思います。
| カテゴリ | 必須アイテム | 解説 |
|---|---|---|
| 服装 | 白衣・輪袈裟・脚絆 | 汚れたらその都度手洗いし清浄を保つ |
| 参拝具 | 金剛杖・納札・経本・数珠 | 杖キャップで先端を保護し境内を傷つけない |
| 防寒防暑 | 速乾タオル・レインウェア | 四国は急な雨多し、通気性優先 |
| ヘルスケア | 絆創膏・テーピング | マメ対策で快適歩行 |
| IT | モバイルバッテリー・オフライン地図 | 電波の弱い山間部対策 |
この上記の服装や持ち物を参考にしていただければと思います!
まとめ
徳島県阿波市
四国八十八ヶ所霊場
第九番札所 正覚山 法輪寺夢にまで見た四国遍路。歩き始めた時はちょっと浮かれていたんです。。二番三番と歩いていくうちに、大変な事を始めたもんだと気付きました
これにて東京に帰ります。
お大師様の前のベンチに腰掛け、またすぐに来ますと約束しましたpic.twitter.com/hA5LpOfG4Q
— A@御朱印 (@ASAKO50769076) June 18, 2025
今回は「四国遍路のやってはいけないルールとは?八十八ケ所巡礼の基本と逆打ちの極意を徹底解説!」と題して紹介してきました!
四国遍路八十八ケ所巡礼は、順打ち・逆打ちどちらでも「感謝と謙虚さ」が鍵になります。
山門一礼から納経までの基本作法を守り、やってはいけないルール10選を避けることで88ヶ所霊場の功徳が真に宿ります。
逆打ちに挑むなら、季節・交通・装備を綿密に計画し、道中の静寂とご利益を存分に味わいましょう!
※こちらの動画も参考に!